PTA�e�r�r�[�`�o���[�{�[�����
2019/06/08
�U���W���i�y�j
�@�ߑO���̑̈�قŁAPTA�e�r�r�[�`�o���[�{�[�����J�Â���܂����B
�@�Q���҂́APTA�̖{�������A�����ۑ̕��̊F�l�Ƌ��E���B
�@���N�́AALT�̃w�C�f���搶�Ƌ�����K�̎��C�搶���Q�����܂����B
�@PTA�̊F�l�Ƌ��E���łS�l���̍����`�[����Ґ��B
�@�T�`�[���ɂ��10�|�C���g�P�Z�b�g�}�b�`�̃��[�O��i���������j���s���܂����B
�@�����̃`�[�����A�S������A���Ŏ��{�B
�@������������炵�Ȃ�����A�݂�Ȉꐶ�����ł����B
�@���N���[�V�����Ƃ͂����A�����������n�܂�ƁA�ǂ̃`�[����������ڎw���ĕK���Ƀ{�[����ǂ��܂����B
�@�D�v���[�A���v���[�����o���܂����B
�@�y�X�|�[�c��ʂ��āAPTA�̊F�l�Ƌ��E�������Ɋy�������Ԃ��߂����܂����B
�@���Q���A�����͂����������F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B
 |  |  |
������K�I�����R���̎��K���̊F����A�悭�撣��܂����I
2019/06/07
�U���V���i���j
�@�R���̑�w���̊F����̋�����K���A�{�������ɏI�����܂����B
�@�T��20���ɃX�^�[�g�����R�T�Ԃ̎��K�́A�ǂ��������ł��傤���B
�@����A�R���̎��K���̓����i���ʗ��K�j�̎��Ƃ��Q�ς��܂����B
�@���C�搶�̂Q�N�Q�g�̉p��i�Q���ځj�A��ؐ搶�̂P�N�R�g�̔��p�i�R���ځj�A���R�搶�̂P�N�Q�g�̐��w�i�U���ځj�B
�@���ꂼ��̎w�������̐搶���玞�Ԃ������Ďw�����A���Ƃ̖ڕW��w�����j�A�w���W�J���L�����ڍׂȊw�K�w���Ă��쐬���Ď��ƂɗՂ݂܂����B
�@������̎��Ƃ��A���k�������w�K�̂߂��Ă𗝉����A�W�����ĉۑ�ƌ��������A�ӗ~�I�Ɋ�������f���炵�����Ƃł����B
�����ꂼ��̎��Ƃ̊T�v�́A���̂Ƃ���ł����B
�����C�搶�̎���
�E���ȁF���w
�E�N���X�F�Q�N�Q�g
�E���ԁE�ꏊ�F�Q���ځE�Q�N�Q�g����
�E�w�K�̂߂��āFwill���g����������\���\���𗝉����A��b����B
�E���Ƃ̗l�q�F�P���Ԃ�ʂ��āA���k�����͐搶�̘b���������蕷���A�ӗ~�I�Ɋ������܂����B���[�N�V�[�g���g�����C���^�r���[�Q�[���ł��A����������ĐϋɓI�ɘb�������A�y�����p�ꊈ�����s���܂����B�搶�ɂ�锭��E�w����������₷���A�����̐��k������グ�Ĕ��\����ӗ~�I�Ȏp���������܂����B
����ؐ搶�̎���
�E���ȁF���p
�E�N���X�F�R�N�R�g
�E���ԁE�ꏊ�F�R���ځE���p��
�E�w�K�̂߂��āF�ዅ�̊ۂ݂��ӎ����A���̂��Ȃ��ł������B�F�����L���g���Ă������B�i�Â��������邢�j
�E���Ƃ̗l�q�F�ڂ�͎ʂ��ĐF�n�ŃA�N�������ʁi�d�˓h��j����ۑ�̂S���Ԗځi�͎ʁF�P���ԁA���ʁF�R�^�S���ԁj�B�߂��Ă̖��m����}��A��l�ЂƂ�̍��ɉ������ʎw���J�ɍs���܂����B�Â����̒��ŁA���k�����͏W�����Ē��ʂ��s���܂����B���k�̍�i���w���̎��̍�������Ă��܂����B
�����R�搶�̎���
�E���ȁF���w
�E�N���X�F�P�N�Q�g
�E���ԁE�ꏊ�F�U���ځE�P�N�Q�g����
�E�w�K�̂߂��āF�l���̍��������v�Z�ƕ��z�@�����ł���B
�E���Ƃ̗l�q�F���߂ɂ������̗��Ő������A���k�����́A�l���̍��������v�Z�̗��K���Ɉӗ~�I�Ɏ��g�݂܂����B�������킹�́A���k�����ɏ����čs���܂����B�u�ړ����k����ł��v�Ɛ搶�������ƁA���k�����݂͌��ɋ��������������J�n���܂����B�߂��Ă̒ƐU��Ԃ芈�����m���ɍs���܂����B
�����k�����ƂƂ��Ɋ������鎞�Ԃ��ł��邾�����������ƁB
�@���ꂪ�A�����̃I���G���e�[�V�����œ`�������Ƃł����B
�@
�@���ƁA�x�ݎ��ԁA���H��|���̎��ԁA�������ȂǁB
�@���k�Ƌ��Ɋ������Θb���钆�ŁA�����̂��Ƃ��w���Ƃł��傤�B
�@������Ă邱�Ƃ̊y�������сA���b��ƂƂ��ɁA��������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���Ƃ̐i�ߕ���k�Ƌ��Ɋ�������p�����āA�ǂ������ɂȂ�Ǝv���܂����B
�@������A���k����w�Ԉӎ������������Ă��������B
�@�����āA�O�d������ψ�������u�����Ƃ��ċ��߂�l�����v��ڎw���A����ɕw���d�˂Ă��������B
�@�R�T�Ԃ͂����Ƃ����Ԃɉ߂��Ă��������Ƃł��傤�B
�@�����F����Ƙb�����Ԃ��A�����Ǝ������������Ǝv���܂��B
�@�̈�Ղ╶���ՂȂǁA���Z�ł���Ƃ��͂ǂ������Ă��������B
�@���C����A���R����A�����̍���̂������Ƃ����K�A�������S�������Ă��܂��B
�y�����Ƃ��ċ��߂�l�����z
���ߘa�Q�N�x�i�ߘa���N���{�j�O�d�������w�Z�����̗p�I�l�������{�v���m�O�d������ψ���n��蔲��
������ɑ����M�Ǝg���������l
�@�q�ǂ��ɑ��鈤��⋳��҂Ƃ��Ă̐ӔC���������A��Ɏq�ǂ��̐l�i�ƌ��d�����w�����ł���l
�����I�m���E�Z�\�Ɋ�Â��ۑ�����\�͂����l
�@��Ɏ��Ȍ��r�ɓw�߁A�q�ǂ��ƂƂ��ɉۑ�Ɏ��g�ޑn�����A�ϋɐ��A�s���͂����l
�����������Љ�l�Ƃ��Ă̖L���Ȑl�Ԑ������l
�@�D�ꂽ�l�����o�ƎЉ�l�Ƃ��Ă̗ǎ��ɕx�݁A�g�D�̈���Ƃ��ĊW�҂Ƌ��͂��ĐE�ӂ��ʂ����A�q�ǂ���ی�҂Ƃ̊Ԃɐ[���M���W���z����l
���ʐ^�́A�U���U���i�j�̓����̎��ƕ��i�B
�����玭�C�搶�i�p��j�A��ؐ搶�i���p�j�A���R�搶�i���w�j�̎��ƁB
 |  |  |
�������̒�~���ԁm13���i�j�܂Łn�����ԃe�X�g��13���E14��
2019/06/06
�U���U���i�j
�@���ԃe�X�g�𗈏T��13���i�j�E14���i���j�ɍT���A��T�ԑO�̍������畔�����͒�~���Ԃɓ���܂����B
�@���̗��K���Ȃ��A���k�����͂������������Ɠo�Z���܂����B
�@
�@���ی�́A�������߂��ꕔ�̕������̂݁A�Z���Ԃ̗��K�����{�B
�@�قƂ�ǂ̐��k�́A�U���̓��ۂ��I���Ĉ�ĂɉƘH�ɒ����܂����B
�@�u���悤�Ȃ�I�v�u���悤�Ȃ�I�v�c
�@���C�Ɉ��A�����āA�F�B�Ƙb�����Ȃ���A���čs���܂����B
�@�U��10���i���j�E11���i�j�ɂ́A���ی�̎���w�K�u���C�����v���J����܂��B
�@�Q���͎��R�ŁA�w�K���e�͊e�����p�ӂ��܂��B
�@�w�N�̐搶�������ɂ��āA���k����̎���ɉ����܂��B
�@�e���Ȃ̃e�X�g�͈͂́A���T�̌��j�i�R���j�ɔ��\����܂����B
�@�e�������Ă��u�w�K�v��\�v�ɏ]���A�ƒ�w�K�ɂ���������g�݂܂��傤�I
�y�e�X�g���{���ȁz
���U��13���i�j��
���P�N��
�@�@����@�A�Љ�@�B����
���Q�N��
�@�@���w�@�A���ȁ@�B�p��
���R�N��
�@�@�p��@�A�Љ�@�B����
��13���͋��H������܂���̂ŁA���ƒ�ŏ��������肢���܂��B
���U��14���i���j��
���P�N��
�@�@�p��@�A���w
���Q�N��
�@�@����@�A�Љ�
���R�N��
�@�@���ȁ@�A���w
��14���̂R���ڈȍ~�͂U���ڂ܂ł̕�����ƂŁA���H������܂��B
 |  |  |
��U�X��ɐ��s���w�Z�t�G�A�����㋣�Z���j�������U�ʁI
2019/06/05
�U���T���i���j
�@�����A�Z���Ԃ̍~�J������܂������A���k���������Z��Ɍ��������ɂ͓V��͉��ē܂��ƂȂ�܂����B
�@�����āA�����O������͐���ƂȂ�A���Ă�������������������Ƃ�A�u�₩�ȕ������㋣�Z��ɐ����܂����B
�@
�@�I�肽���ɂƂ��Ă��A�����̐��k�����ɂƂ��Ă��A��D�̃R���f�B�V�����̒��ŁA�`������A�����㋣�Z���J�Â���܂����B
�@���́A���N10���Ƀ��j���[�A���I�[�v�������O�d��ʂf�X�|�[�c�̓m�ɐ����㋣�Z��ł����B
�����N�́A��N�ɑ����āA�I��E�⏕���ɉ����āA�s��11�̒��w�Z�̑S�Z���k�������ɎQ���B
�@���Z�̑I�肽���̉����ƂƂ��ɁA�w�Z�ԂŃG�[�����������A�݂��Ɍ𗬂�[�߂܂����B
�@�����̐��k�����́A�I�����W�F�̃��K�z�����g���Ă���������̐���U��i���Đ����𑗂�܂����B
�@�uISUZU JHS�v�̃^�I���������ɐU��A�S�Z���k�̔M���v����`���܂����B
�@�����c�̐��k���K���ł����B
�@���ۂ�ł��k�̎�ɂ͂܂߂��������ł��܂����B
�@�o�ꂵ���I�肽���́A���������S�Z���k����̉�����w�ɎāA�S�͂ő���A���сA�����܂����B
�@�I��c�Ɖ����̐��k���S����ɂ��āA�ڎw���͌��E�˔j�I
�����ʁA�{�Z�́A�e��ڂ̃|�C���g�̍��v�ŁA���q�����T�ʁA�j�q�����U�ʁA�j�������U�ʂł����B
�@��ڕʂł́A���q��22��ڒ�17��ڂŁA18�l�ƂQ�`�[���i�����[�̊e�S�l�j���A�W�ʂ܂ł̓��܁B
�@�j�q��23��ڒ�12��ڂŁA11�l�ƂQ�`�[���i�����[�̊e�S�l�j���A�������W�ʂ܂ł̓��܂��ʂ����܂����B
�@�܂��A�j�����������[�̂P�`�[���i�S�l�j�����܂��܂����B
�@���߂łƂ��I
�@���ȃx�X�g���X�V�����I����������܂����B
�@�悭�撣��܂����I
�@����̑��ŁA���Ă�͂��\���ɔ����ł����A�������v���������I����������ƂƎv���܂��B
�@����A���̉��������o�l�ɂ��ė��K���d�˂܂��傤�B
�@�����āA���̑��ł́A����̖ڕW���B���ł���悤�Ɋ撣��܂��傤�B
�@�⏕���Ƃ��ĎQ���������k�������A�P����ʂ��āA�悭�撣���Ă��܂����B
�@�����ɗ��Ă����������ی�҂̊F�l�A���肪�Ƃ��������܂����B
�y���܂̊T�v�z
����������
���W�ʂ܂ł����܁B�s�����w�Z����11�Z�B
���j���������U��
���P�ʂ��珇�ɁA�����A�����A�ɐ��{��A���l�A�q�c�R�A�\��A�`�A��c
�����q�������T��
���P�ʂ��珇�ɁA�����A�����A�ɐ��{��A���l�A�\��A�`�A��c�A��
���j�q�������U��
���P�ʂ��珇�ɁA�����A�q�c�R�A�����A�ɐ��{��A���l�A�\��A�`�A��c
���l����
���W�ʂ܂ł����܁B
���u���ʁv�͊w�N�I�[�v���̎�ځB
�����q��
�����Ґ��F18�l�ƂQ�`�[���i�����[�̊e�S�l�j
�E�y����100���z�V�ʁA�y�P�N100���z�U�ʁA�y�Q�N 100���z�R�ʁE�W��
�E�y�Q�N200���z�P�ʁE�R��
�E�y����800���z�V�ʁA�y�P�N800���z�T��
�E�y��w�N�i1�E2�N�j�S�~100���q�z�Q�ʁA�y���ʂS�~100���q�z�U��
�E�y���ʑ������z�V�ʁA�y�Q�N�������z�R��
�E�y���ʑ������z�W�ʁA�y�P�N�������z�V��
�E�y���ʖC�ۓ��i2.721kg�j�z�R�ʁE�U�ʁA�y�Q�N�C�ۓ��i2.721kg�j�z�U��
�E�y���ʉ~�Փ��i1.0kg�j�z�U��
�E�y���ʃW���׃��b�N�X���[�z�W�ʁA�y�P�N�W���׃��b�N�X���[�z�P��
���j�q��
�����Ґ��F11�l�ƂQ�`�[���i�����[�̊e�S�l�j
�E�y����100���z�P�ʁA
�E�y����200���z�Q�ʁE�V��
�E�y����400���z�T��
�E�y�Q�N1500���z�T��
�E�y��w�N�i1�E2�N�j�S�~100���q�z�S�ʁA�y���ʂS�~100���q�z�U��
�E�y�P�N�������z�V��
�E�y���ʖC�ۓ��i5.0kg�j�z�P�ʁA�y�Q�N�C�ۓ��i5.0kg�j�z�T��
�E�y���ʉ~�Փ��i1.0kg�j�z�Q��
�E�y���ʃW���׃��b�N�X���[�z�P�ʁi���V�L�^�j
�E�y�P�N�W���׃��b�N�X���[�z�T��
���D�G�I��܁F�P���i���ʃW���׃��b�N�X���[�j�����V�L�^�F62��84
���j��������
�����Ґ��F�P�`�[���i�����[�̂S�l�j
�E�y�����S�~200��R�z�S��
�y����̃r�b�O�C�x���g�z
��2020�N�i�ߘa�Q�N�j�F�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N
��2020�N�i�ߘa�Q�N�j�F�S�����w�Z�̈���
�����C�u���b�N�S���i�O�d���A���m���A�É����A���j�ł̊J�Âł��B
���J�Ê��Ԃ́A�ߘa�Q�N�W��17���`25���B
���O�d���ł��A���㋣�Z�A�o�X�P�b�g�{�[���A�T�b�J�[�A�̑����Z���J�Â����\��B
��2021�N�i�ߘa�R�N�j�F��76���̈���^��21��S����Q�҃X�|�[�c���
���O�d���ł́A���a50�N�ȗ�46�N�Ԃ�̊J�Âł��B
���J�Ê��Ԃ́A
�@�����̈���F�X��25���`10���T��
�@��Q�҃X�|�[�c���F10��23���`25��
�����́F�O�d�Ƃ��킩����
���X���[�K���F�Ƃ��߂��Đl �����₢�Ė���
 |  |  |
�s�s��A�����㋣�Z���@���悢�斾���I
2019/06/04
�U���S���i�j
�@�A�����㋣�Z���𖾓��ɍT���A�U���ڂ̑̈�قŁA����ɑ����ĂQ��ځA�����čŌ�̑S�Z���k�ɂ�鉞�����K���s���܂����B
�@���̌�A�I��c�����シ��s�s����s���܂����B
�@�I��c���A�S�Z���k�̑傫�Ȕ���Ɍ}�����đ̈�قɓ���B
�@�X�e�[�W��ɁA�����ɐ��܂����B
�@�j�q�E���q�̃L���v�e�������A�B
�@���ꂼ��̖ڕW��͋������܂����B
�@�����āA�����c���ƍZ�������A�B
�@�I��c�̊���ւ̊��ҁA�S�Z���k�ɂ�鉞���̈ӋC���݂�`���܂����B
�@�����āA�����c���A�S�̂������������ȉ������I���A�w�Z�S�̂őI������サ�܂����B
�y�I��c�ւ̃��b�Z�[�W�z
�@��69��ɐ��s���w�Z�t�G�A�����㋣�Z���A���悢�斾���ƂȂ�܂����B
�@���㕔�𒆐S�Ƃ��āA�������̘g���đI��c���Ґ�����A�F����́A���A�[���A���K���@���H�v���āA�݂��ɋ��͂��ė��K��ςݏd�˂Ă��܂����B
�@�����́A���̐��ʂ���������Ɣ������Ă��炢�����Ǝv���܂��B
�@���ꂼ��̎�ڂœ��܂�_���A�܂��A���ȃx�X�g�X�V��ڎw���āA���Ă�͂��o���邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ċ撣���Ă��������B
�@���N10���ɐV�������㋣�Z�ꂪ���j���[�A���I�[�v�����A��N�R�N�Ԃ�ɁA�s���S���w�Z�̑S�Z���k�ɂ�鉞���������B���N�͂��̂Q�N�ڂł��B
�@���N�̉����c��82���B��N��57����傫������剞���c�ƂȂ�A�����A�����x�݂ɗ��K�𑱂��Ă��܂����B
�@�N���X�ł́A�����c�̐��k�������ɗ��K�ɍs����悤�ɁA�W�̎d������������`�����肵�āA�����c���������邱�Ƃ��������ƕ����Ă��܂��B
�@�܂��A���N�́A����܂ł̂V��ނ̉����p�^�[���ɁA�V���ɂS�̉����̂��������܂����B
�@�_�C�i�~�b�N�����ARPG�AStaRt�A�A�t���J���E�V���t�H�j�[�B
�@���k��̈ӋC���݁A���C�������܂��B
�@����ɁA�uISUZU JHS�v�̃^�I�������́A���Z�ɂȂ��{�Z�Ǝ��̉����ł��B
�@�����́A�����c�̃��[�h�̂��ƂŁA�S�Z���k����ۂƂȂ��āA���̊w�Z�����|����悤�ȉ��������Ă���邱�Ƃł��傤�B
�@�I��c�̊F����́A�S�Z���k�̔M��������w�ɎāA�\�钆�w�Z�̑�\�Ƃ��Đ���t�撣���Ă��������B�������F��܂��B
 |  |  |
�S�Z�������K�^�U���ځ��A������͖�����A�s�s��͖����I
2019/06/03
�U���R���i���j
�@�A�����㋣�Z������ɍT���A�S�Z���k�ʼn������K���s���܂����B
�@�I��c�������A�����c�ƈ�ʉ����̐��k���A�U���ڂɑ̈�قɏW�����܂����B
�������c�̐��k��82���B
�@�S���������͂��܂��Ɋ����A������܂𒅂�����A�{���|�����������肵�ď������[�B
�@�̈�ق̃X�e�[�W�O�Ɨ��T�C�h�ɗ����܂����B
�@�c���A���c���Ȃǂ̉����c�̃��[�_�[�́A�X�e�[�W�ɏオ���đS�̗��K�����[�h���܂����B
����ʉ����̐��k�́A�I�����W�F�̃��K�z���Ɛ��F�̉����^�I���������A�̈�ق̒����ɏW���A���܂����B
�����K�z���́A����傫��������A�U������A��̂Ђ��ł��ĉ���炵���肵�Ďg���܂��B
�����F�̃^�I���́A��N�x���牞���Ɏ����ꂽ���̂ŁA�uISUZU JHS�v�̕��������F�ň������Ă��܂��B
�@�U������A����A�g�̂̑O�ōL�����肵�Ďg���܂��B
�@�^�I�����g���������́A�X�|�[�c�ϐ��R���T�[�g�Ȃǂł悭�����܂��B
���S�Z���k�ɂ�鉞�����K���n�܂�܂����B
�@�����c�̒c���╛�c���Ȃǂ̃��[�_�[���X�e�[�W��ɗ����A�}�C�N���g���ĉ������@�����������A���̏o�����⓮���̌��{�������Ȃ�����K�͐i�߂��܂����B
�@�t���A�����ʉ����̐��k�����̗l�q�����Ȃ���A�������X���[�Y�ɂ����Ȃ������ɂ͕ύX���������܂����B
�@�܂������A�uThe activities of the students, by the students, for the students�v�B
�@���k�́A���k�ɂ��A���k�̂��߂̊����ł����B
�@���K���J��Ԃ����тɁA���⓮���͑傫���Ȃ�A������Ă����܂����B
�@�݂�Ȃ̋C��������ɂȂ��Ă����悤�Ɋ������܂����B
�@�����́A�I��ւ̉����ƂƂ��ɁA�w�Z�ԂŃG�[���̌������s���܂��B
�@�v�X�A�C���̂������������ɂȂ邱�Ƃł��傤�B
�@�A�����㋣�Z���́A������U���T���B
�@�����̂U���ڂɁA�̈�قős�s����s���܂��B
�@�s�s��ł́A�S�Z���k�̋C������I�肽���ɓ`���܂��傤�I
�@�����āA�o�ꂷ��I��̊F����́A�S�Z���k�̊肢��v����w�����āA�\�钆�w�Z�̑�\�Ƃ��Ċ撣��܂��傤�I
 |  |  |
�ߑւ����S���{�����悢���
2019/06/03
�U���R���i���j
�@�u���͂悤�������܂��I�v�u���͂悤�������܂��I�v
�@�����炱���炩��A���C�Ȓ��̈��A���������Ă��܂��B
�@���k�����́A�����甒�������̃|���V���c�𒅂ēo�Z���܂����B
�@��������ߑւ��̊��S���{�ł��B
�@�{�Z�ł́A���N�U���P����10���P�����ߑւ��̓��Ƃ��Ă��܂��B
�@�������A�C��̏ɉ����āA���̑O��ɁA�ĕ��E�~���̂ǂ���ł��悢�ڍs���Ԃ�݂��Ă��܂��B
�@���N�̉Ă̈ڍs���Ԃ́A�T��13������31���܂łł����B
�@���̊��Ԃ́A�ĕ��̃|���V���c�ł��A�~���̏㒅�ł��A�ǂ���𒅗p���Ă��\���܂���ł����B
�@�����č�������A�㒅�ɂ��Ă̓|���V���c�̒��p�ƂȂ�܂����B
�@�|���V���c�́A���̖��n�ő����Ƀ��u���t���Ă�����̂ƂȂ��Ă��܂��B
�@�܂��A���D�����S�s���ŕt���邽�߁A���|�P�b�g�t���̂��̂������߂ł��B
�@�Y�{����X�J�[�g�͉ėp�E�~�p�̂ǂ���ł��\���܂���B
�@���悢�揋���Ă�����Ă��܂��B
�@�M���ǂȂǂɋC��t����ƂƂ��ɁA�߁E�H�E�Z�̐���������K���ɂ��C��z��A���N�ň��S�ȉĂ��߂�����悤�ɐS�����܂��傤�B
���ʐ^�͂P�N���̒��w���̗l�q�B
��������A�P�g�A�Q�g�A�R�g�B
 |  |  |
�A���~�ʁ��x���}�[�N����^�U���E��P���k�� PRESENTS
2019/06/03
�U���R���i���j
�@����̎�������ł́A�ی�҂̊F�l�A�n��̊F�l�ɑ�ς����b�ɂȂ�A���肪�Ƃ��������܂����B
�@���k�����������̎��ƂƂ��Ĉꐶ�����Ɋ������܂����B
�@
�@�ߑO���͓܂�Ŋ����ɂ͍œK�̂��V�C�ł������A�������I���Ă��炭�o�����ߌ�Q��������͉J���~��n�߂܂����B
�@�T�����̍����́A���k�������o�Z���钩�̎��ԑт����܂�̂��V�C�ł������A����ɓV��͉��Đ���̂P���ƂȂ�܂����B
�@�u���͂悤�������܂��I�v
�@����t�߂ɗ����Ă���ƁA�o�Z���Ă��鐶�k��������A���C�Ȓ��̈��A���������Ă��܂��B
�@�����́A�U���̃A���~�ʁE�x���}�[�N����̂P��ځB
�@���k�����́A�A���~�ʂ̓������召�l�X�ȑ傫���̃r�j�[���܂��g���ēo�Z���܂����B
�@�{�N�x�́A���k���̒�ĂŁA�����̃A���~�ʁE�x���}�[�N����̓����Q��ݒ肳��Ă��܂��B�������U���̂Q��ڂł��B
�@�P��ڂɎ����ė���̂���������Y�ꂽ�ꍇ���A�����̂Q��ڂɎ����Ă��邱�Ƃ��ł��܂��B�����A�C�f�A�ł��B
�@���k�����������ė����A���~�ʂ́A�e�K�̑��ړI���ɗp�ӂ��ꂽ�N���X�ʂ̑傫�ȑ܂ɂ܂Ƃ߂��A�����x�݂ɁA�����E������������q�ɂɒu���ɍs���܂����B
�@�x���}�[�N�ɂ��ẮA���̎��ԂɁA�N���X�̃x���}�[�N�ψ����_���ʂɎd���������āA����܂Ɏ��߂Ă��܂����B
�@�A���~�ʂ́A������x���܂����i�K�ʼn���Ǝ҂̕��Ɏ��ɗ��Ă��������A���v���͐��k�̊�����ɂȂ�܂��B
�@�x���}�[�N���A�W�܂����_���ɂ���āA�w�Z�ŕK�v�ȕ��i�Ɋ����邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�ی�҂̊F�l�A�n��̊F�l�ɂ́A�{�N�x�������͂���낵�����肢���܂��B
 |  | 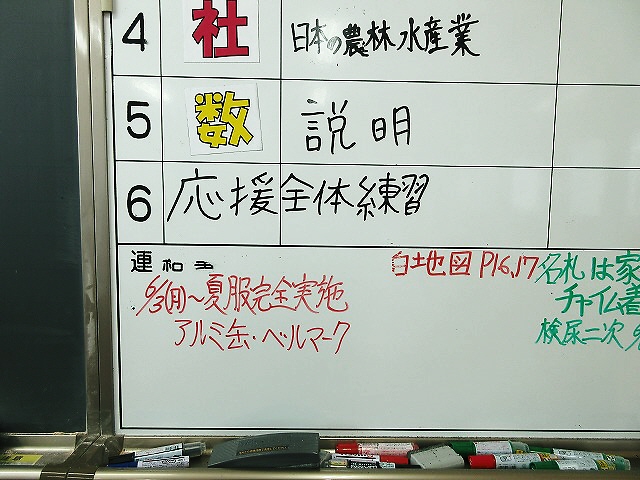 |
��P��������ی�҂̊F�l�A�n��̊F�l�A�L��������܂����I
2019/06/02
�U���Q���i���j
�@�o�s�`��Â̖{�N�x��P��ڂ̎���������s���܂����B
�@������̓܂��B��D�̎���������a�B�V��Ɍb�܂�܂����B
�@�M���ǂ̐S�z�����Ȃ����̒��Ŋ������邱�Ƃ��ł��܂����B
�@���k�����́A�ߑO�������̎��ƂƂ��āA�����n��͂W������ی�҂̊F�l�ƈꏏ�Ɋ����B
�@16�̒n��E�W�Ϗ��ʂɉ����ƂɎ��g�݂܂����B
�@���k��{�������A�����E�������A�w��O����̒ʊw���k���͒�����w�Z�ɏW�����A�e�n�悩��^��Ă������������R���e�i�ɐςݍ��݂܂����B
�@�e�n��ł̍�Ƃ��I�������R�N���́A�����A�w�Z�ɏW�܂�A�ςݍ��ݍ�Ƃɍ������܂����B
�@�V�����A�G���A�i�{�[���A�A���~�ʁA�����p�b�N�A�z�ނȂǁc�B
�@�e�n��ŁA���k�ƕی�҂̊F�l�����ɉ����Ƃ����{�B
�@�ی�҂̊F�l���A�y�g���b�N���p�ԁA��^�g���b�N�ŁA��Q�W�Ϗ��̌\�钆�w�Z�Ǝl�����w�Z�ɉ^��ł��������܂����B
�@
�@��Q�W�Ϗ��ɎԂ��������ăh�A���J������ƁA���k�����́A�ו���f�����Ԃ���~�낵�āA�R���e�i�ɐςݍ��݂܂����B
�@�ǂ̐��k���ꐶ�����ł����B
�@�V����G�����u�͂��v�ƌ����Ď��ƁA���k��������u���肪�Ƃ��������܂��I�v�Ƃ������t���Ԃ��ė��܂����B
�@�u���������čs���܂��I�v�ƌ����A���悵�Ă�������̎�����������ĉ^�т܂����B
�@�\�钆�w�Z�̐��k�����́A�悭�����܂��B
�@���w�Z�ł̍�Ƃ̒��߂�����ł́A�W���������k�����ɁA�o�s�`��̒������炲���A�����������܂����B
�@���k�����̓����Ԃ�ւ̂˂��炢�ƁA����̊����ɑ��錃��B
�@�ی�҂��\�����D�����ɂ��ӂ�邨���t�ł����B
�@�ی�҂̊F�l�ɂ́A�������玑������ɂ����g�݂��������A���肪�Ƃ��������܂����B
�@���Ԃ�������������Ƃ�����A��Ϗ�����܂����B
�@�o�s�`�{�������E�e�ψ��̊F�l�ɂ́A�����i�K�����ς����b�ɂȂ�܂����B
�@��������ɂ����͂����������n��̊F�l���ɂ����ӂ������܂��B
�@
�@��������������͊������A���k�����̕������⋳�犈���Ȃǂ̌o��Ƃ��Ċ��p�����Ă��������܂��B
�@���Ƃ̕��X��n��̊F�l�̂����͂Ŋw�Z����̏[�����}���Ă��܂��B
�@���k�̊F����́A���̂��Ƃ��Ċm�F���A���ӂ̋C������Y�ꂸ�ɐ������Ă����܂��傤�B
 |  |  |
�������琅�����i�݂ȂÂ��j�������͑�P�����
2019/06/01
�U���P���i�y�j
�@��������U�����X�^�[�g���܂����B
�@���A���z��i����j�̂U���̘a�������i��ӂ����߂��j�͐������ł��B
�@�R���͏�������܂����A���̈�Ɂu���̌��i�u���v�́u�́v���Ӗ�����j�ŁA�c�ɐ����������̈Ӗ��v�Ƃ������̂�����܂��B
�@���{�ł́A����������葾�z��i�V��j���̗p����A12�������P������12���܂ł̐����ŕ\���Ă��܂��B
�@����ȑO�͋���ŁA�G�ߊ���������悤�Șa���������g���Ă���A���̂U�Ԗڂ̌����������Ƃ���Ă��܂����B
�@�a�������͋���̋G�߂�s���ɍ��킹�����̂ŁA���݂̗�ł��g�p����邱�Ƃ�����܂��B
�@�������A���݂̋G�ߊ��Ƃ͂P�`�Q�����قǂ̂��ꂪ����܂��B
�@�w�Z�ł́A�Ɩ����̐��R���A�v�����^�[�̉Ԃ̐A���ւ������܂����B
�@���낢��Ȏ�ނ̉Ԃ��A���R�ƐA�����Ă��܂��B
�@����A�����������̐��k�������A����������Ȃǂ̐��b�����܂߂ɂ��邱�Ƃł��傤�B
�@���ꂩ��~�J�̋G�߂��}���܂��B�����āA�����Ă̓����B
�@���̊ԁA�ԁX�͓��X�傫���������A���X�ɐV�����Ԃ��炩���A�������̖ڂ��y���܂��Ă���邱�Ƃł��傤�B
�@�����́A��P��̎�������ł��B
�@���k�����́A�ߑO�������̎��ƂƂ��āA�ی�҂̊F�l�Ƌ��Ɋ������܂��B
�@�ی�҂̊F�l�A�n��̊F�l�ɂ͗l�X�����b�ɂȂ�܂����A�ǂ�����낵�����肢�������܂��B
 |  |  |


